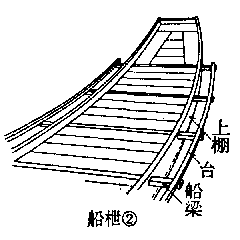せがいづくり【船枻造り】
「建築大辞典」(彰国社)より
近世の民家において側柱上部から腕木を突出して小板を張った棚をもつもの。
和船の両舷にある舟棚(船枻)に似ているのでこの称が出たものと思われる。
組頭・名主層以上の住宅にしか許されていなかったもので、階層が上がるに従い両船枻・三方船枻・四方船枻となり、郷士や割元庄屋では二重船枻が付けられることもあった。
単に「船枻」ともいい、地方によって「せんげ」、「せげえ」、「せえげ」、「せげ」、「ひかい」、「せんがい」ともいう。
京都の町屋では同構造のものを加敷造り(かしきづくり)と称する。→ひじきせんげ →のぼりせんげ →さがづくり
せがい【船枻】
「広辞林」(三省堂)より
船の左右両舷(げん)に渡した板。
船頭がこいだり、さおをさしたりする所。ふなだな。
──────────────
「建築大辞典」(彰国社)より
盆の縁(へり)形式の一。鏡部分から口辺までの部分で反りのある縁。このような盆を青盆という。
和船の上船梁の舷外突出部とそれに組合わせた台(縦通し材)とで構成される張出し部のこと。
中世まではこの上に踏板を置き櫓(ろ)を漕ぐ場所としたが、近世では同様の構造でも漕手は上棚内部に置くため、張出しは少なくなり、また弁才船(べんざいぶね)のように櫓走(ろそう)をしない船が主力となってからは、単に船べりの意味にも使うようになった。→せがいづくり