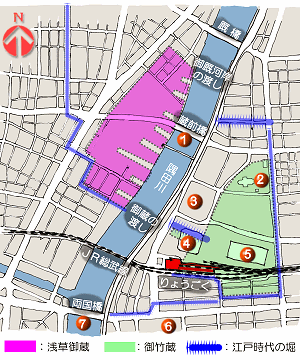明治時代の地図を見ると「御竹蔵」がそっくり利用されているのが良くわかる。 南側は総武線の始発駅「両国」とその引き込み線が描かれていて、「秋葉原」と並んで割り堀を利用した物流運搬基地だったことが読み取れる。しかしその後、総武線と中央線が繋がることにより秋葉原が物流ターミナルとなりその陰に隠れてしまった。しかし千葉以東へ向かう多くの列車が始発駅としていたため、長らくターミナル駅として活況を呈していた。(1972年以降は東京駅始発となる)
北側を占めているのが陸軍・被服廠の建物群である。共にこの引込堀が利用されたことを示していて、江戸時代の切り絵図からは大きく堀が延長されている事からも、この堀の重要性が良くわかる。ちなみに当時の被服廠は東京・大阪・広島の3ヵ所に配置されたが、被爆地広島には奇跡的に建物が現存している。詳しくはこちらからどうぞ。
蔵前橋
「蔵前橋通り」(都道315号御徒町小岩線)が渡ることにちなんだ橋。 右岸の墨田区「蔵前」と左岸「横網」をつなぐ橋である。
蔵前橋というと橋の右岸にあった蔵前国技館(正字体:藏前國技館)を思い浮かべるが、それは昭和59年(1984)までのこと。現在の国技館は左岸の両国に移っている事は周知のことだろう。そのため国技館附近の墨田区横網(よこあみ)を横綱(よこづな)と長い間読み間違えていた。
右岸の墨田区蔵前は江戸初期からあった「浅草御米蔵」(幕府の米蔵)があった所で、幕府の直轄地(天領)からの年貢米を収蔵することにちなんだ地名である。
この橋の歴史を調べてみたら、意外にも関東大震災の復興計画で架橋され、それまでは「富士見の渡し」として渡船場があったところだった。
たまたま橋の補修中だったので、この黄色に塗装された色は下地の色?位にしか思っていなかったら、なんと米蔵の「稲の籾殻」をイメージして選ばれた色とのこと。川を行き来する船のための「安全色」が本当のことではなかろうか。高欄には「力士」や「姉さん」のレリーフがはめ込まれているが、竣工当時の写真にはなかったので戦後の「蔵前国技館」完成と併せて取り付けられたものだろうか。
さて、橋を渡ると横網町で、関東大震災や東京大空襲を今に伝える「横網町公園」がある。
▲Back to Map
関東大震災の記憶・(横網町公園)
大正12年(1923)9月1日午前11時58分に発生した関東大震災では、死者・行方不明者 : 142,800名 負傷者 : 103,733名、住家被害 : 全壊128,266戸、半壊126,233戸、焼失447,128戸という壮絶な被害をもたらしている。
この地はかつての陸軍被服支廠が赤羽台に移り、そのあとを公園にと工事が始まったばかりであった。下町では貴重な広い公園地だったことにより数万人の人々が避難することとなった。しかし直後に起こる周りの火災で、その数4万人といわれている方々が亡くなられた。当時の写真を見ると遺体があちこちに山のように積まれて悲惨なことを物語っている。(写真集のリンクを貼っておきます) そのほとんどは火災旋風が発生することにより、高温のガスや炎を吸い込み窒息死したものと見られている。
ちなみに阪神・淡路大震災では、死者:6,434名 行方不明者:3名 負傷者:43,792名、住家被害 : 全壊104,906戸、半壊144,274戸、焼失6,148戸
(データはフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』による)
そしてこの悪夢は昭和20年の東京大空襲で繰り返されることになる。B29による絨毯爆撃により焦土と化した人口密集地下町のこの避難地域はまた多くの死者を出すことととなった。3月10日の大空襲1日だけでも死者・行方不明者が10万人を超えるという。
回向院(えこういん)
江戸城をはじめ、市中の大部分を二日間にわたって焼いたといわれる明暦の大火(1657)で焼死者108,000体を葬るために建立された寺だが、天明元年(1781)以降、境内で勧進相撲が行われたことから、今日の大相撲の起源となっている。
寺の出自からわかるように、あらゆる無縁仏を宗派にこだわることなく埋葬し、さらには動物全ての供養もするという寺である。寺の正称はなるほどと思わせる「諸宗山無縁寺回向院」
大相撲と関係が深いことから明治42年(1909)には同じ境内に初代両国国技館が建設された。この建物は当時としては巨大なドーム天井を持つ建物で、その形から大鉄傘(だいてっさん)の愛称で知られるものだった。しかし大正6年(1917)の出火・火災、大正12年(1923)の関東大震災、昭和20年(1945)の東京大空襲、と焼失と再建を繰り返してきた。さらに戦後は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)により接収され、接収解除(1952)の時には蔵前国技館の工事が始まっており、国技館としては不運な歴史を背負ってきた。そして最後は「日大講堂」となり、昭和57年(1982)の解体で不運な建物の歴史を閉じている。
設計は辰野金吾と教え子・葛西萬司
▲Back to Map
△Back to Top
Mozilla, Chrome, Opera & I.E. に対応(20150123)
参考文献:
「江戸切絵図 今昔散歩」 佐々悦久・野村秀夫・菊池明 著
「家康はなぜ江戸を選んだか」 岡野友彦 著
「年表・隅田川」 真泉充隆 著