���h�_��
�@���̐_�Ђ̑n���͑�όÂ��A���ÓV�c��N(601)�Ɠ`����B���̌�A������̊���(933)����n�܂�����̑��c���J��Ԃ���A���c���̖k�����͓�\�ѕ��̐_�̂��A����ƍN�͓l���̔n�����i�A�_�n����q�A�ƌ��͏\�O�̎��̂���i�E�E�E�Ɛ_�А�����ɂ������B
�@�͊ݒi�u�̂܂��ɐ쉏�ɂ���̂����̐_�ЂŎQ���͐�����ɂ��ĉ��X�Ƒ����Ă���B
�]�ˎ���̓x�d�Ȃ��i�͋ʐ�㐅���̏㗬�ɓ����邱�̒n��ɂ���v�f�ƍl������B���̍L�X�Ƃ����쉏�ɐ_�n�����q����A�l�̋߂Â��Ȃ�����ɂ����̂��낤�B
���ʗp�̐���삩�狂��ł��痧�ĊŔɋC�t���A�v�킸����␂�ł��܂����B
�w���̂�����}���V���o�܂��B���ӁI�x
��ɂȂ��čl������A����͌���̐���ɂ��邽�߂̎�i�������̂��E�E�E�E�E�H
��TOP
�H���̖��ƁE�����c��
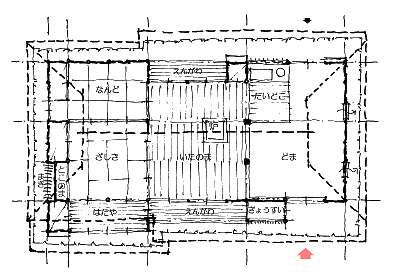
���ʐ}
�@�H���̑�\�I���Ƃ��H���s���y�����ٗ��Ɏc����Ă������B
�����c�Ƃ́A�O��4�N(1847)�Ɍ��z���ꂽ���ꉮ���E�������ƂŁA���̒n���̈�ʖ��Ƃ̎p�𗯂߂Ă���E�E�Ɛ��������ɋL���Ă���B
�����ɂ͍��ł��������Đl���Z��ł����Ԃɕۂ��Ă��āA�K�⎞�ɂ��d���ĂׂĂ������B���ꉮ�̑���Ȃ̂Ő^�~�͂��Ȃ茵�������Ƃ��낤���璋��͓r��邱�Ƃ͂Ȃ��������Ƃ��낤�B���̊ԗ��̃j�b�`��̏ꏊ���d�u��ƕ������ďZ�l�̙{���ʂ���������ꂽ�B
�@�����(���)�e�̏������͍s��������Ƃ���Ƃ̂��Ƃŏ��͒|�̃X�m�R�łł��Ă���B����ɂ��̉�(����)�ɂ͉����y�Ԃɖ��ߍ��܂�Ă��ĕ��ۂŋ��ݏo����悤�ɂȂ��Ă���B�_��Ƃ���A�������Ƃ̐g�̗����ɋM�d�Ȑ���厖�Ɏg�������Ƃ��z�������B�����͕֏����Ǝv�������A�̂͌ˊO�ɕʌ����ł������̂��낤�B
���āA��������H���̉��ɓ���
�@�ʐ�㐅�͉H���̉�����]�ˎl�J��،˂܂Ő���������43km�A���፷��92m�Ƃ����A���ςɂ��Č��z1/500�Ƃ����ɂ₩�Ȍ��z�𗄂݂Ȃ������B�����Ă��̗��ꂪ������ƍr��ɋ��܂ꂽ�������n�̂قڕ����E�i�����j�𗬂��o�H����邱�ƂŁA��n�̕\�ʔr�����㐅�ɒ������ƂȂ��]�˂ɓ�����Ă��邱�Ƃ�m��ƁA�����̑��ʂ����߂Ƃ����l�X�ȓy�؋Z�p�ɂ͋����������̂ł���B
�@���̍H�����V�����i�P�N���Ƃ�����������j�Ƃ������Z���ԂŐ��������Ă��܂����Ƃ��������̋Z�p�Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂������̂��낤���H�H���s���y�����قł�����x�͂킩�������̂̂قƂ�ǂ͋L�^���Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA�z�����邵���Ȃ��̂��B
�@���݂͉��������ɂ��̓�H���𐬂��������p�Y�Ƃ��āu�ʐ�Z��i���E�q��E���E�q��j�̑��v�����Ă��Ă���B
���������̓`���̉p�Y���ӊO�ɂ��B���ꂽ���j�����邱�Ƃ�m�����B
�ʐ쐅�_�ЂƐw����
�@�ʐ쐅�_�Ђ͓��������̎��_�ŁA�ʐ�㐅�������O�N�Ɋ��������ہA���_�{�Ƃ��Ă��̒n�Ɍ������ꂽ���̂ł���B���͑O�ʂ̓��H������ʼnH������������Ă���B
�����Ă��̏㐅�̊Ǘ������Ă����̂��w���Ə̂�������ŁA���݂́u�����s�����ljH���搅���v�Ɩ��̂�ւ��Ă��̖���S���Ă���B���̂��Ă̖�i�w����j�����_�Иe�Ɏc����Ă���B
���̊Ǘ���E�́A�]�˂��疾���ɕς��Ƃ��Ɉ����p�����X���[�Y�ɍs���悤�����p����A���̌�͐��P���ōs���Ă���Ƃ̂��Ƃ��ȑO�ǂ����̎����œǂL�������邪�����������낤���B
��TOP
�H���搅���E��ꐅ��E���
�@��ꐅ��͑����삩��̎������A���͎����ꂽ���������ɗ�������ł���B���̒��Ԃɂ͑������ɐ���ɗ��ꍞ�]���Ȑ���y���𑽖���{���ɔr�o���鏬�f����i���f���E���͂������j������B�����ő��̐��ʂ̑������Ƃɂ͂т�����ŁA���ꂪ�S���ʐ�㐅�ƂȂ�̂ł��낤���H
�@�搅���Ƃ͐�������~�߂Đ����������ނ��̂����A�_���̂悤�Ɋ��S�ɉ����~�߂�̂łȂ��ۑ��E�Ȃǂɂ���Ă��Ȃ�̐��ʂ�R�炵�Ȃ����荞�ނ悤�ɂȂ��Ă���B�]�˓�������̕��@�����ł���������Ă���B�X�ɂ͂��̏ꏊ�͏㗬�̍ޖ������ɗ����v���ł�����A���̂��߂̏ꏊ���m�ۂ��ꂽ�B�����̈ʒu�ƋZ�p�͊�{�I�ɂ͕ς�炸�p����Ă���B
��ꐅ��͓��ނ̍\���`���ō\������Ă��āA��O�̐���͂��̒��ł͐V�����i���a�̂��́H�j�Ɛ��@�����q�b���̂��̂ƁA������ԌÂ��i�����̂��́H�j�Ǝv���郌���K�ɂ��g�ϑ��ŋ��`�A�[�`�Ŋ|���n���ꂽ���̂�����ł���B�f�o����Â�������Ɠ������̂��̂��낤���A�����A�[�`�`���̐Α��ł���B
��TOP
���l��
���̋��͂��Ă̌ܓ��s�X���ɉ˂��鋴�Ƃ��āA��������d�v�Ȃ��̂ł������B���̂��ߖ������ɂȂ�ƐΑ��̂߂��ˋ��̎p�ʼn˂���ꂽ�����Ƃ����B���݂̍����͓���̂悤�Ȍ`�����Ă��邪�A�[��썂���̂Ȃ��肩�H����A�����������������̂��낤���H
���̐�i�E��j�̉������X�����z����Ƒ�����ɏo�āA�吳���܂ł������Ƃ����u���l�̓n���v���o�āA�ܓ��s�Ɏ���Ƃ����̂������̊X���ł������B�i���݂͌F�싴���́u�������v�œn�邱�ƂɂȂ�j
�ܓ��s�X���͂i�q�����ܓ��s�w�O���琙���捂�~����i�~���j�Ő~�X���ɍ�������܂ł̖�42�q�̊X�����������A���݂ł͕ČR���c��n�ŕ��f����Ă��āA���̕ӂ�͂��̃��[�g��H���Ă��悭����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���B
���l��
���݂̋��l���́A���a52�N3���ɉ˂��ւ���ꂽ���̂ł���܂��B
���l���́A�����ƍb�B�����Ԍܓ��s�X���ɉ˂��鋴�Ƃ��āA�n�Ԃ⋍�Ԃ̉����ɂ��ݗ��̖؋��ł͔j���������A�Ǘ���̕��S�͑�ςł����B
���������ɐV���{�������s�̋ߑ㉻��}�邽�߂ɌF�{���H�������A��d�����͂��ߖ؋���m���̊ዾ���ɉ˂��ւ������Ƃ������������Z�����A���l���Ɏ�����A����10�N12���ɁA�߂��˂��ƈ��̂��ꂽ���l���͌��݂���܂����B
����4�N�x�ɍs�����ʐ�㐅�����Q�����ł́A�ƒ�����p���ė��j�I���i��������A�e���⍂���A�����ܑ��̉��P�Ȃǂ��s���܂����B
���@�@���@12.5m
���@�@���@11.3m
�\���`���@PC�v���e���V�������Ō���
�ːݔN���@���a52�N3��
��TOP
����y�i�݂����炢�ǁj
�@���������O�ł���B�u����y�v�Ə����āu�݂����炢�ǁv�ƓǂށB�q���w�߂��̂��̂�����i���E����y�����j�͉͊ݒi�u�i����i�u�j�̒[�ɂ�����A���݂͂i�q�~���Ɣ������ŋ��܂ꂽ��������]���B
�@���Ă͋ʐ�Z��ɂ��㐅�̎搅�ɁA����������Ŏ��s�A���ɕ����s�F�삩����������A���̒n�Ő����n���ɋz�����܂�Ă��܂����Ƃ��������`��������B���ꂩ��u�݂����炢�ǁv�u�݂������ǁv�ƌĂꂽ�Ƃ����B
�@�H��������쓌�ɗ���Ă����ʐ�㐅�͂��̂�����i����i�u�R���j���瓌�̕��Ɍ�����ς��邱�ƂɂȂ�B���̊J��H���Ղ͊R���ɉ������H�������̋z�����ݑw�ɓ������Ď��s�������߁A�x��V���ɖk�Ɉڂ������c�ł���B���̂��ߐV�����@��ꂽ�ʐ�㐅�̉E�݂ɂ͐l�H�I�ȓy�肪�q���w�߂��܂Œz����Ă��āA�R���̑��}�������̂Ǝv����B
�@���āE�E�E�q���w���ԋ߂̌F��܂ŗ��Ă��܂�������A������Ɗ�蓹���Ă݂悤�B
��TOP
�ΐ��
�@���v3�N�i1863�j�Ɏn�܂�Ƃ������̑������B�����������͑�����Ί݂̏��쑺�Ŏn�܂�A�������̓c���Ƃ͓X���W�ł������Ƃ����B����14�N(1881)�ɂȂ��Č��ݒn�̌F��Ɏ𑠂����ĂĂ���ꏊ���ڂ��A���݂܂�120�N�]��̗��j�����B
�n�Ɠ����̏��W���́u���d���v�ł��������A����͏��쑺�̐X�c�́u���d�e�v�Ǝo���W���������O�Ƃ̂��ƁB�吳�W�N(1919)�Ɂu���d�~�v�ɉ����A���a8�N(1933)���猻�݂́u���������v���g�p���Ă���B�i�����َ����ɂ��j
�@���ʑ剮���̌��������̒n�ł̑��Ɠ�������́u�{���v�ŁA�E��̑��͖���30�N(1897)����n���Ɏg���Ă���u�V���v�B�����́u���ɑ��v�i�����̌����͑S�č��o�^�L�`�������j
�ΐ�Ƃ́A����19�N(1886)���疾��23�N(1890)�ɂ����ČF�쑺���Ƌ��ɋЂP���A�����Qkm�̕����x�i�F�앪���j���������B���̈�\�͕~�n���Ɍ`�𗯂߂Ă��āA���Ă͐��Ԃ��݂����A���Ă┭�d�ɗ��p����Ă����Ƃ����B
�@�v�w�O�͎���400�N�ɂȂ��ł���B�������K�ɁA���Ă̐_�l�i�单�l�j�Ɛ��̐_�l�i�ٓV�l�j���J���Ă���B�����F��ł́A��l�̐_�l��v�w�Ƃ��Ă����߂�M������Ƃ����B
�@�X�ɉ��ɍs���ƁA�Ɍ������Ȃ��������ވ�˂���_�Ə̂����̘e�ɕۑ�����Ă����B�̂���̌����`���Łu��̉��ɂ͗ǂ������N���v�ƌ������������A����700�N�����Ƃ������̌�_�̉��ɂ��������������N���A��˂����Ă����̂��낤���H
�ΐ�͂Ȃ�Ɩ���21�N(1888)����u���{�����v(�p�����x����JAPAN BEER)�̏��W�ŁA�r�[���̏������n�߂Ă���B
�����A���胂���g���ύ����̂��낤���E�E�E�g���Ă����劘���c����Ă����B������i�[���Ă��錚�����u�������̊فv�ŁA�T��ɑ劘�̗R�����L���Ă������B
��
�@������\�N(1887)�ΐ�ł͂��������r�[���̏������J�n�u���{�����v�̏��W�Ŕ�������
�@�o�א�͒n���A���l�A��z�A�[��A�ԍ�c���A�n�A�����ƍL�͂Ȃ�����������Ȃ���̂����܂�ɂ����������ł��������Ȃ�������ނȂ��킸���O�N�ŏ����͒��~���ꂽ
�@���́u�������̊فv�͂���ȗ��j�̏Ƃ��Ċ�����S�N�ڂɓ������㔪���N�A����J���R�搶�ɐv���˗��������������̂ł���
����@�ΐ�픪�Y
�y���@�߁z�@���{�̔����̗��j�͖����ɂȂ��Ă���ŁA
�@����18�N(1885)�@�L�����r�[��(JAPAN BREWERY)�́u�i�فv
�@����20�N(1887)�@���{�����́u�G�r�X�r�[���v
�@����21�N(1889)�@�T�b�|���r�[���́u���b�h�X�^�[�v
�@����22�N(1889)�@��㔞���́u���v
�E�E�E�Ɓ@���̎���Ɍ��݂Ɍq���������������Ă���B
�@�@�i���������ڂ������������������j
�@�ŋ߂̒n�r�[���l�C���炾�낤���A�ΐ�������n�r�[���u�����̌b�v�Ƃ��ĕ���10�N�ɕ������Y���Ă���B
���̑������͓c���ƈ���ĂȂ��Ȃ������M�S�ŁA�~�n���Ƀp�u��X�g������p�ӂ��A���̏�Ŋy���܂��Ă����B���������n�r�[������͏�ʔ��y�́u�y�[���G�[���v���A�n���ł͏��Ď��́u�F���Ԓn�v�𒍕��A�{���͂���ɂăX�P�b�`�͏I���B
��Back to Top
Mozilla, Chrome, Opera & I.E. �ɑΉ��i20150123�j